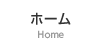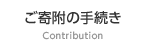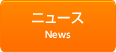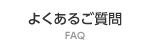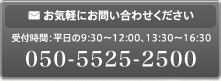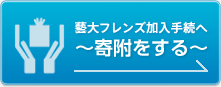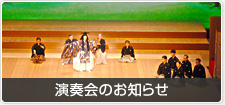隔年開催の「創造の杜 藝大現代音楽の夕べ」は、審査を経て選出された作曲専攻の大学院生による2作品と、作曲科専任教員による新作、計3作品の世界初演に加え、藝大と関わりの深い作曲家の代表作再演という、いずれもオーケストラ作品によるプログラムで構成されています。本学における作曲教育・研究の成果を社会に発信する場であるとともに、その創作の歴史を顧みる貴重な機会でもあり、前回に引き続き今回も藝大フレンズ会員の皆様よりご支援を賜り、本公演を開催いたしました。
今回再演されたのは、世界的に著名で、本学と深い関わりをもつ作曲家・西村朗氏(一昨年逝去)による代表作です。プレトークでは、同氏と親交の深かった作曲家・池辺晋一郎氏と、本学作曲科教員・金子仁美が登壇し、軽妙な語り口で故人の人柄を偲ぶ内容となりました。
プログラム冒頭には、この春、大学院修士課程を修了した廣庭賢里による作品《MONOlith⇄MONOlogue》が置かれました。同作は、奏者による身体的パフォーマンスや発話を伴いつつ、2群に分割されたオーケストラにより、思想的・内面的なメッセージ性の強い表現を試みたものであり、同時にある種の躍動感を内包する作品でもありました。
続く前半2曲目には、作曲科専任教員による新作として、折笠敏之による《transformatio emergens II》が初演されました。特に弦楽器に関して演奏が極めて困難な作品でしたが、ジョルト・ナジ本学特別招聘教授の指揮のもと、藝大フィルハーモニア管弦楽団による真摯な演奏により、アコースティックな創作にコンピュータを援用した素材生成と変容、その推移を通じた独特な音響世界が展開されました。
演奏会後半の冒頭には、廣庭と同じく今春修士課程を修了した林梨花による《Where is She?》が演奏されました(十七絃箏ソロは、現代箏曲専攻を卒業し、今年度修士課程に進学した鹿野竜靖)。能「二人静」から着想を得つつ、音楽作品における過去と現在の関係性、和洋の境界という観点から、自身の表現を比較的小規模な編成のオーケストラによる端正な書法で追求した作品でした。
大学院修了の若手2名によるこれらの作品は、作曲専攻において各自が研鑽を積む中で抱いた創作上の問題意識や姿勢を明確に示しており、修士課程在学中に各々が能動的かつ主体的に取り組んだ成果が、作品に結実していることが窺えました。
そして演奏会の最後には、西村朗氏の代表作《2台のピアノと管弦楽のヘテロフォニー》(1987)が再演されました。本学ピアノ科教員の實川風と、ベルリンを拠点に国際的に活躍する北村朋幹の両氏によるオーケストラとの競演は、圧倒的な熱量と迫力で聴衆を惹きつけ、演奏終了後には会場の奏楽堂が、500名近くのお客様による盛大な拍手と歓声に包まれました。多くの方がこの作品の再演を目当てにご来場されたことが窺えました。
最後になりましたが、本公演の開催にあたり、藝大フレンズ会員の皆様より賜りましたご支援に心より感謝申し上げます。頂いた賛助金は、本公演の運営経費の一部に充当させていただきました。今後とも、本学の教育・研究活動へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
東京藝術大学音楽学部作曲科

プレトーク:池辺晋一郎、金子仁美の各氏により、西村朗氏の生前のエピソード等が語られました。

廣庭賢里:《MONOlith⇄MONOlogue》 オーケストラのための (2024-25世界初演)

折笠敏之:《transformatio emergens II》 (2025 世界初演)

林梨花:《Where is She?》 十七絃箏とオーケストラのための(2024-25世界初演)